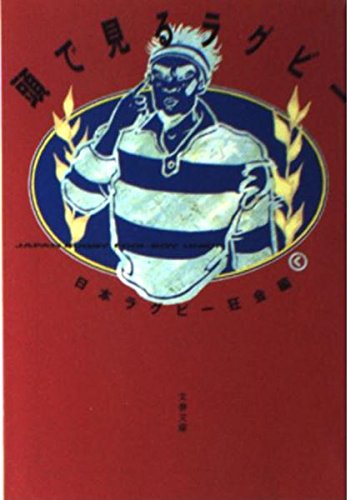ラグビーについて多くの本を出版している日本ラグビー狂会ですが、そのかなり早い時期の本です。
1995年出版で、第3回ワールドカップ開催を前にした頃です。
当時はまだまだ世界のラグビーとの格差が大きすぎました。
その割に、大学ラグビーの人気は高くテレビでも中継され会場には満員の観客が押し寄せていました。
ただし、社会人ラグビーはまだまだ人気が出るにはほど遠く、現在の状況とは全く違います。
そんな頃の各段階のラグビーについて、ラグビー狂会の多くの論客が厳しく指摘します。
対象は、大学、社会人、高校、レフェリー、国際環境です。
大学ラグビーはまだまだ早明が中心。帝京など名前も出てきません。
しかしその少し前の全盛期からはかなり実力低下とされています。
すでに大東文化大学などには南太平洋勢が入ってきており、徐々に勢力図が変わってきているところでした。
社会人も人気ではまだ大学ラグビーにはるかに引き離されていましたが、ニュージーランドやオーストラリアからコーチ兼任のベテランが招聘されて入部するということが始まっていました。
しかしそれをフルに活かすという方向ではなく、彼らの出場を制限するといった愚策に走るという姿が見られました。
高校ラグビーは現在でも同様でしょうが、トップクラスの実力は徐々に上がっていったのですが、各県せいぜい1校から2校程度しかまともにラグビーをプレーできず、県大会では100点ゲームどころか200点ゲームも続出していました。
相手チームは怪我などしないように立ったまま。トライ後のゴールキックは時間短縮のためにドロップキックで行ったということです。
国際的な状況では、日本は一流二流どころにはまったく歯が立たなかった時期です。
その対策を考えるにも差があり過ぎてどうしようもありませんでした。
本書内にあくまでも冗談として書いてありますが、強国から一流プレーヤーを連れてきて日本でも当時一級のアスリートであった女子バレーボール選手との子どもを作らせるのが唯一の対策ではとあります。
そうかもしれません。
現在は状況がかなり違ってきており、日本と諸外国の強力チームとの差が縮まっているように見えますが、これは言うまでも無く国際的な出場選手資格の変更により、日本代表として海外出身選手が出場しやすくなったからというのは明らかでしょう。
ただし、念のために書いておきますが、これは日本だけの特例ではなく全世界すべてに適用されており、海外チームでも自国出身者だけで代表チームを構成しているのはごく一部だけです。
まあどのような経緯であっても上質な試合が見られるようになったことは楽しいものです。
ただし、眼ばかりが肥えてしまい大学ラグビーなどはちょっと物足りなく感じてしまいます。