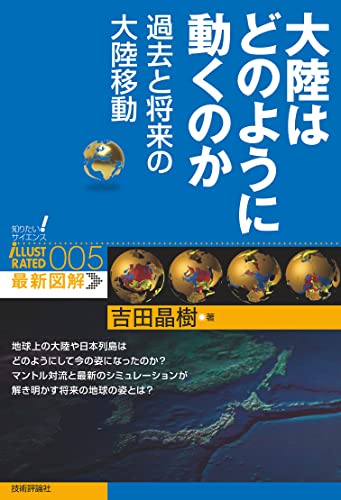1912年にウェゲナーが大陸移動説を発表した際にはほとんどの学者はそれを信じませんでした。
しかし現在ではプレートテクトニクス理論を疑うものはほとんどいないようです。
その間、多くの研究が為され大陸を移動させる原動力となるのが地球内部のマントル対流らしいということは分かってきました。
その一つの現れとしてプレートが動いています。それに伴い火山爆発や地震が発生することも理論が間違いないことを示しています。
ただし、地球内部の構造やその動きはそれを調べる方法が非常に難しいためにまだまだ分からないことが多いようです。
そういった地球科学(固体地球科学と言うそうです)の研究の最先端情報をまとめられています。
ただし、著者あとがきにもあるように、こういった情報をこの先固体地球科学を目指したい中高生に向けてこの本を書いたということで、もはや年老いた読者は相手にしていないのかもしれません。
そのせいか、本書の活字は非常に小さく、年寄りには読みにくいものになっていました。
章題をみれば本書の大まかな構成は判るかもしれません。
第1章「プレート運動と”地殻変動”」
第2章「大陸移動からみた地球の内部」
第3章「大陸移動から見た地球の歴史」
第4章「将来の大陸移動の予測」
第5章「日本列島形成史、将来の日本列島」
第6章「将来の地球の予測」
となっています。
大陸移動説の頃には分かっていなかったこと、マントル構造やその運動などが徐々に分かってきたのですが、まだまだ分からないことばかり、若い人たちにこの分野の研究を目指してもらいたいという熱意は感じられます。
大陸移動説に時代にも、かつて地上の大陸がすべて一つに固まっていた「超大陸」というものが在ったと言われていました。
しかし現在ではこれまでの地球の歴史上、3回超大陸が形成されていたそうです。
それが18億年前から16億年前までの「コロンビア」、10億年前の「ロディニア」、3億年前の「パンゲア」でした。
パンゲアの名前しか知りませんでした。
これらの超大陸は周期性があるかのようです。
6から8億年間隔で形成され、いったん形成されると1-2億年程度の持続期間があり、その後分裂していく「超大陸サイクル」というものがあるのではと言われています。
将来の大陸の姿がどうなるかという研究もおこなわれています。
再び超大陸サイクルによってそれが形成されるのかどうか。
しかし別の研究によれば地上の海水が約6億年後には無くなってしまうという可能性も指摘されています。
もしも海水がなくなれば海洋プレートの沈み込みもなくなり、やがてはプレートテクトニクスも完全に停止してしまいます。
大陸は砂漠化し地表は高温となってしまうでしょう。
さらに別の研究によれば地球上の二酸化炭素は徐々に低下しある濃度を下回ると植物の光合成ができなくなり、全ての生物が絶滅してしまうとか。
逆に二酸化炭素が増え続け、金星のように灼熱地獄となるとも。
もしも少年時代にこの本があったなら、地球科学を目指していたかもしれません。