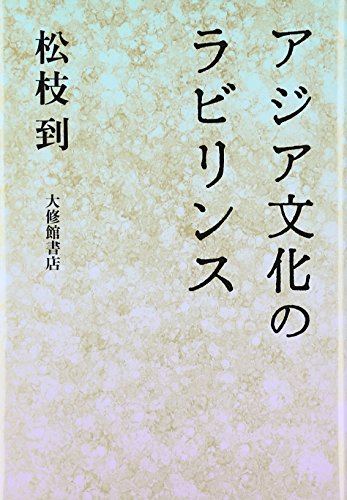この本はアジア文化史が専門の著者が、大修館書店から出版されていた「月刊しにか」という雑誌に1997年から2003年にかけて連載されていた、「キタイ周遊」という連載全60編をまとめたというものです。
アジア全体についての様々な問題に関連し思いつくことを書き連ねるという体裁となっています。
対象地域は中国が多いようですが、他にも中央アジア、アラブ、日本など様々です。
またそのきっかけとなるものはアジア発であっても連想ははるか世界に飛び回るということも多く、あちこちに広がっています。
孫悟空という存在について書かれた文章、「もうひとりの悟空」はもちろん現在ではあの「ドラゴンボールの悟空」を思い浮かべる人がほとんどでしょうが、それ以前であれば西遊記に登場する悟空であったことでしょう。
しかし歴史上の実在の人物でやはりインドから仏典を中国にもたらした孫悟空という人物がいたということはあまり知られていないようです。
玄奘が18年にわたるインドへの旅で仏典を中国にもたらしたのは西暦628年のことですが、その100年余り後の世にもインドに派遣された官吏の一行があったそうです。
その中の一人が孫悟空という人物で、彼もその後長い時間をかけてようやくインドから経典を持ち帰ることができたそうです。
江戸時代、富永中基という人物がいたということはあまり知られていないことでしょう。
「出定後語」という著作を残し、わずか32歳で1746年に亡くなりました。
生きている間にはほとんど知られることもなかったのですが、その後の学者がこの著作を発見し取り上げたことで有名になりました。
東洋史学者の内藤湖南がくりかえし富永のことを語り、彼の天才ぶりを称揚していたということです。
この著作「出定後語」は一言で言えば仏教批判の書であり、仏典を検証すると現状の仏教界は体制を守ることだけに汲々としているだけだと批判したのでした。
その本の評判を聞いた平田篤胤が本屋を巡り歩いても見つけることができず、ようやく蔵の奥に死蔵されていた本から見つけ出したとか。
彼の生涯の詳しい評価はまだできていないのではないかとされています。
なかなか趣深い文章が並んでいました。
ちょっと難しいものもありました。